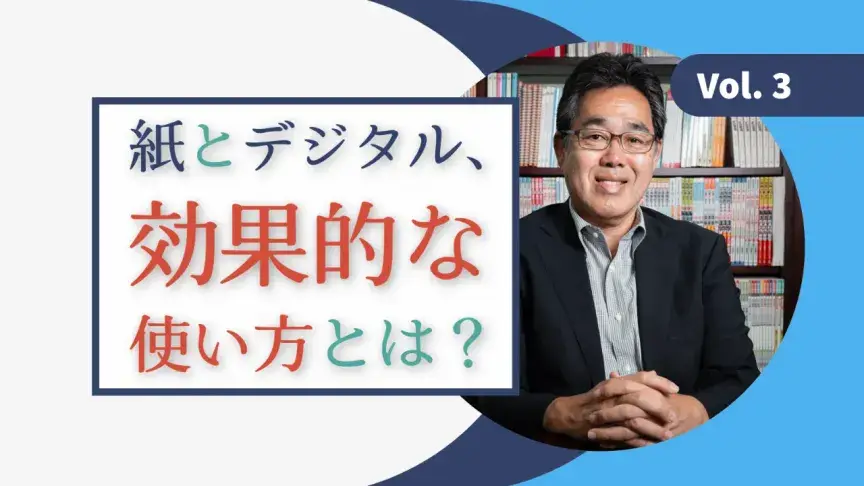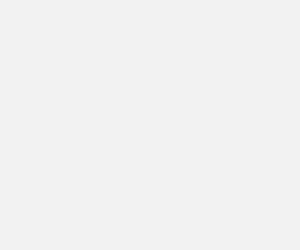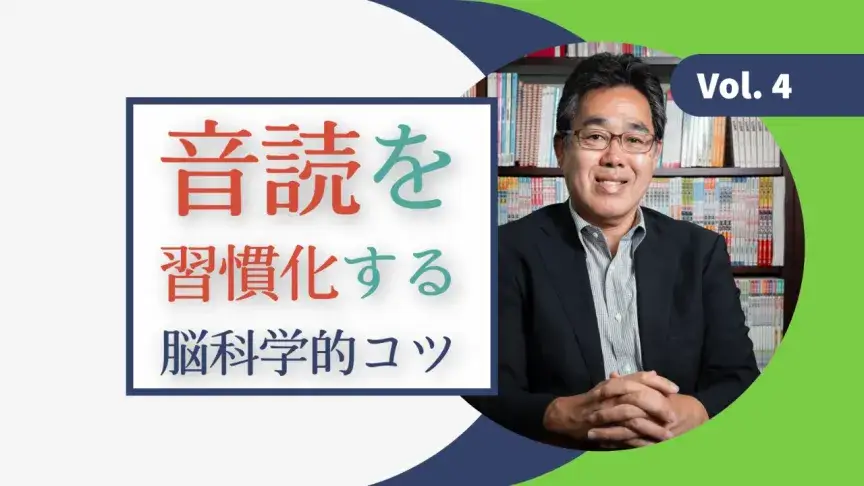
音読は、認知症予防や英語学習に効果があるとわかっていても、「続けることが難しい」と感じている人は少なくない。特にシニア層にとっては、モチベーションや生活習慣の壁が立ちはだかることも多い。 そこで今回は、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授に、音読の継続を阻む脳の特性と、それを乗り越えるための工夫について話を伺った。
第3回を読む
目次
人間の脳は「同じことの継続」が苦手
まず、なぜ続けることが難しいのか。川島先生は、それが人間の脳の性質そのものだと説明する。
「我々人間は同じことをずっと継続するということは非常に苦手な脳を持っています。すぐに飽きてしまう。どちらかというと何か新しいものに飛びつくというのが私たちの脳の性質です」
実際、脳トレを始めても継続できる人はごく少数に限られるという。
「何か出すと多くの人がワーッと飛びつきますけれども、継続できる人は10%もいません。どんどん人が脱落するんですね」
続けるコツは「目標」と「フィードバック」
では、どうすれば継続できるのか。川島先生は次の2点を挙げる。
まずは目標の設定だ。
「目標を持つということ。それも遠くの目標だとくじけますから、それと近い目標を持って、達成したら次の目標を立てる。これが一つの方法です」
目標設定は本人ができれば理想だが、難しい場合は周囲の支援者が設定をサポートすることも有効だという。
もう一つは、「できたこと」を誰かに認めてもらうこと。
「やりっぱなしだと、誰も褒めてくれない。やっぱりやる気がどんどん薄れてしまう。何かしたときにちゃんとできたということを誰かが認めてくれると、それがすごい力になって、ずっと継続していくことが可能になります」
「やる気」は生活習慣から生まれる
モチベーションを語る上で欠かせないのが、脳の状態。やる気が高まるとき、脳内では何が起きているのか? 「やる気」「モチベーション」を保てる人とできない人の差はどこにあるのか?
「やる気、モチベーションと一口で言っても、実は全く違う2つのものがあります。一つは“内発的動機づけ”、もう一つは“外発的動機づけ”です」
そして川島先生ははっきりと語る。
「学習の効果という観点からいうと、外発的動機づけというのは一切、学習効果がないことがわかっています」
「では、どうやって内側から湧き上がる「やる気」を持ち上げるのか?それがわかれば、教育の世界はバラ色ですが、はっきりしたことはわかっていません。ただし、「やる気スイッチ」がどこにあるかは脳科学的に分かっています。右利きの方なら前頭葉の右側です。ですが、たたいても電気刺激してもスイッチは入らない。子供たちの研究成果から「やる気スイッチ」を入れる方法がいくつかわかっています。 」
内発的なやる気を引き出す方法としては、意外にも「生活習慣」がカギになるという。
「睡眠の習慣、食事の習慣をきちっとしている人たちは、やる気スイッチ、内発的動機が高まりやすいということがわかっています」
つまり、「何を学ぶか」の前に、生活リズムを整えることが最優先なのだ。
「忙しい」は錯覚? 時間の見直しが第一歩
「忙しくて学習の時間がない」と言う人に対しても、川島先生は研究結果に基づいてこう語る。
「今の時代、多くの方はSNSやメールなどで時間を食われていて、それは自分たちの時間が壊れているという意識がなくて、何だか知らないけど時間が足りないというふうに感じているのが現実です」
その上で、こうアドバイスする。
「小学校のときに夏休みに入ると24時間の時間割表をつくったと思うのですけれども、それを一回、自分がどういうふうに時間を使っているかと書いてもらうといい。9割の人が『実は忙しくない』ということに気づくと思います」
続けるには「運動」と同じ感覚で
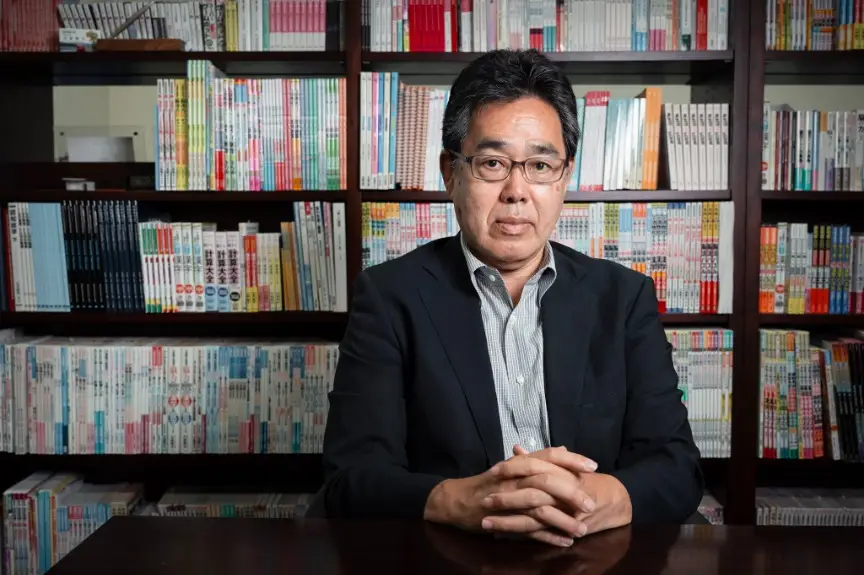
では、英語の音読に取り組むときに、どんなことを意識すればいいのか。
「まず一つは根気よく続けていただくということが大事です。脳だと思うから特別に感じるんであって、体の運動だと思ってもらえば理解できるかと思います」
「脳も全部一緒です。やめると元に戻ります。英語の音読もその一つで、ポイントは“少し早く読む”こと」
さらに川島先生は、「楽しくやりすぎること」への注意点も語る。
「(リズムに乗ってなど)楽しく音読をした場合は、脳トレ効果はないのです。おもしろいことに、楽しさが上回ってくると、どんどん脳の効果が減っていくという、ちょっと困った性質があるんですね」
つまり、脳を鍛えるには「負荷」が必要。走ることと同じで、トレーニングはややきついくらいがちょうど良いのだ。
まとめ|「脳を鍛える音読」を続けるために
音読は、脳を活性化し、認知症予防や学習効果の向上にもつながる優れた方法です。しかし、その効果を最大限に引き出すには、継続的に、適切な負荷をもって取り組むことが必要です。 川島隆太教授が繰り返し強調したのは、次のようなポイントです:
人間の脳は継続が苦手。だからこそ、小さな目標を設定し、達成を積み重ねることが大切。
・やる気(内発的動機づけ)を高めるには、生活習慣の見直しが最優先。
・英語音読をトレーニングとして活かすには、「速く読む」ことを意識する。
・楽しさ重視ではなく、少し負荷をかける意識が効果を生む。
英語でも日本語でも構いません。音読は一日1分でも構いません。“いまの自分”のために、そして“これからの自分”のために、ぜひ今日から声に出す習慣を始めてみてはいかがでしょうか。
【最後に】
このインタビュー連載は今回で最終回となります。全4回にわたり、川島隆太教授にご協力いただき、音読と脳科学の関係について深く掘り下げてきました。ご協力、誠にありがとうございました。